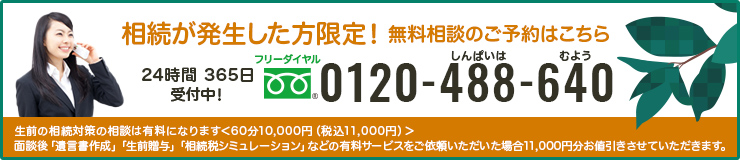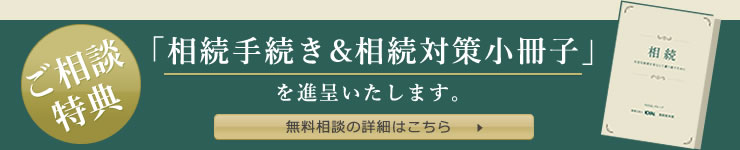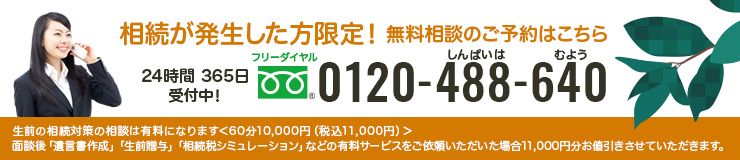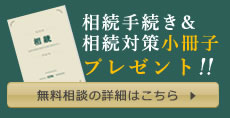遺言書の種類
一口に遺言書といっても、法的拘束力のあるものを作成するには、きちんとした手順をとる必要があります。
作成方法によって名称が異なり、また、取り扱い方法も違ってきます。
取り扱い方法を間違ってしまうと、せっかく書いた遺言が無効になってしまうこともありますので、注意が必要です。
なお、要件を満たさず法的拘束力をもたない遺言書については、相続の指針とはなりますが、強制力がないため、かえって相続人等の争いを引き起こすおそれもあります。
遺言書を作成する場合には、きちんと法的拘束力をもつものを作成することをおすすめいたします。
種類別 作成方法と注意点
遺言書の作成には以下の3つの方式があります。
それぞれに特徴がありますので、メリットやデメリットを考えながら、自分に合った遺言書を作成しましょう!
自筆証書遺言
一番手軽に書ける遺言書であり、費用もかからず、内容を知られることもありません。
ただし、要件を満たしていないと法的には無効となるほか、偽造される心配があるのが難点です。
この遺言書を作成する場合には、保管の仕方を踏まえて検討することが重要です。
また、実際の相続の際には裁判所の検認を受ける必要があります。
秘密証書遺言
遺言書の内容を本人以外誰にも知られずに作成することが出来ます。
また、自筆証書遺言とは異なり遺言者が自筆する必要はありません。
公証役場でその遺言書が真の遺言書であることの確認を行いますので偽造の心配はありませんが、
若干の費用はかかります。 また、実際の相続の際には裁判所の検認を受ける必要があります。
公正証書遺言
公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。
秘密証書遺言より費用はかかりますが、公証人が確認をしますので作成上の不備により無効になるといった危険性や偽造の心配はありません。原本の保管もしてもらえますので紛失・隠匿の心配もありません。
実際の相続の際も裁判所の検認は不要であり、すぐに内容を実行できます。
確実に遺言を行いたい方にはこちらをおすすめします。