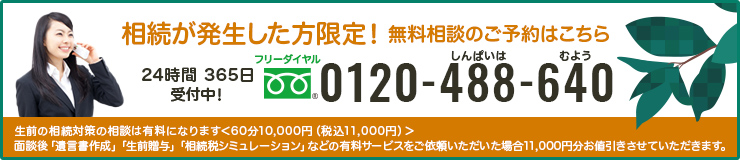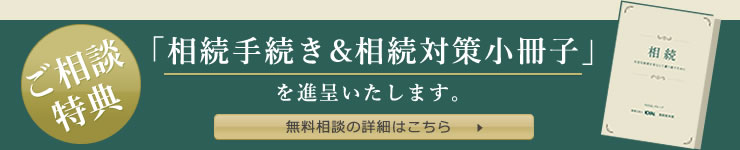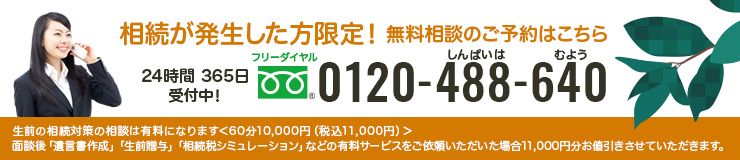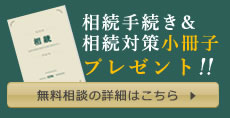お知らせ
所得税だけでない確定申告のポイントについてエッセイを執筆しました(2019.02)
贈与税申告のポイント
確定申告の受付が始まり、私たち税理士もあわただしい日々を送っています。確定申告は、所得税のほか、一定の贈与を受けた場合には贈与税についても必要となります。贈与は、近年の相続税法の大改正から注目されており、申告件数も高水準を保っていますが、贈与税はあまりなじみがない方も多いと思います。今回は、贈与税申告のポイントについていくつか紹介いたします。
1
続きを読む >>
今からできる相続対策セミナーに登壇しました。(12月4日開催)
テーマ:①相続の基本 ②民法改正のポイント ③生前贈与について
開催日時:2018年12月4日
講師:沓掛 伸幸
続きを読む >>
「遺言」と「相続」セミナーに登壇しました。(11月10日開催)
弊社代表税理士 沓掛 伸幸がセミナーに登壇しました。
テーマ:「遺言」と「相続」
開催日時:2018年11月10日
講師:沓掛 伸幸
続きを読む >>
生命保険文化センター様のWEBマガジンに弊社税理士の相続エッセイが掲載されました!
生命保険文化センター様のWEBマガジンに弊社税理士、沓掛伸幸の相続エッセイが掲載されました。
【所得税税制改正】平成30年から配偶者控除が大きく変わります
【2017年分確定申告のポイント】ぜひとも注意したい盲点
【相続税改正その後】大きな変化と知っておきたい相続相談の実際
https://www.jili.or.jp/kuraho/essay/
ぜひご覧ください。
続きを読む >>
相続コラムを投稿しました: 相続税対象者が増えています!
昨日、国税庁が平成27年分の相続税の申告状況についての概要を発表しました。
それによりますと、平成27年中(平成27年1月1日~平成27年12月31日)に亡くなられた方は約129万人で、このうち相続税の課税対象となった方が10万3千人だそうです。相続税の課税対象となる方は亡くなられた方全体の8%となっています。
平成26年の4.4%から大幅に増えています。 東京国税局だけに絞ると、亡くなられた
続きを読む >>
相続コラムを投稿しました: 基準地価 土地の価格は「一物四価」
9月20日に、2016年の基準地価が国土交通省より発表されました。
今日の日経一面でも報道されましたが、商業地は9年ぶりに上昇、住宅地もマイナス幅が減少し、
昨年より引き続き回復傾向にあるようです。
(そうなのか~、となぜか実感がわかないところはありますが・・・)
資産税の仕事をしていると、地価のニュースは非常に重要です。
お客様からのご相談が多い「土地の評価・価格」に直接的に関わってく
続きを読む >>
相続コラムを投稿しました: 生前対策 :遺言作成 よくあるQ&A(2)
前回のコラムに続き、「遺言作成よくあるQ&A」をご紹介します。
年賀状や暑中見舞いは毎年書くことはあっても、「遺言」は一生にそうそう書く機会があるものでは
ありません。
いったい、何からどうすれば?と思われるお客様がほとんどです。
実際のケースでお客様から頂いたご質問を、順に沿ってご紹介していきたいと思います。
生前対策: 遺言作成 よくあるQ&A(2)
続きを読む >>
相続コラムを投稿しました: 生前対策 :遺言作成 よくあるQ&A(1)
TOTAL資産税本部では、相続関連のさまざまなご相談を頂きますが、
最近ご相談頂く機会が増えているのが、「遺言」のご相談です。
「遺言」。
年賀状や暑中見舞いは毎年書くことはあっても、「遺言」は一生にそうそう書く機会があるものでは
ないですよね。
「ずっと作成したいと思っていたんだけど、そもそもどうすれば・・・?と悩んで、そのまま時間が過ぎてしまった」
とおっしゃるお客様が多い印象を受
続きを読む >>
相続コラムを投稿しました: 税理士泣かせの漢字 いろいろ・・・
相続税の申告をするにあたって、ご遺言がない場合など、遺産分割協議書を作成します。遺産分割協議書とは、遺産分割協議で相続人の皆さまが合意した内容を書面に残すものです。相続税の申告書の資料として添付したり、預貯金口座などの相続手続きに使用したりします。この遺産分割協議書を作成するにあたり、税理士泣かせのお名前・漢字がいろいろあります・・・遺産分割協議書 : 税理士泣かせの漢字いろいろ・・・
続きを読む >>
相続コラムを投稿しました: 債務 相続財産からひけるもの(2)
今回は、相続財産からひけるものとして、債務をご紹介します。相続財産から控除できる債務控除の対象には、借入金といったわかりやすいものから、医療費・水道光熱費・未納税金など、様々なものがあります。本当は控除できるのに計上していなかった、、、そんなことにならないように、主な債務控除の対象についてご紹介します。債務 : 相続財産からひけるもの(2)
続きを読む >>